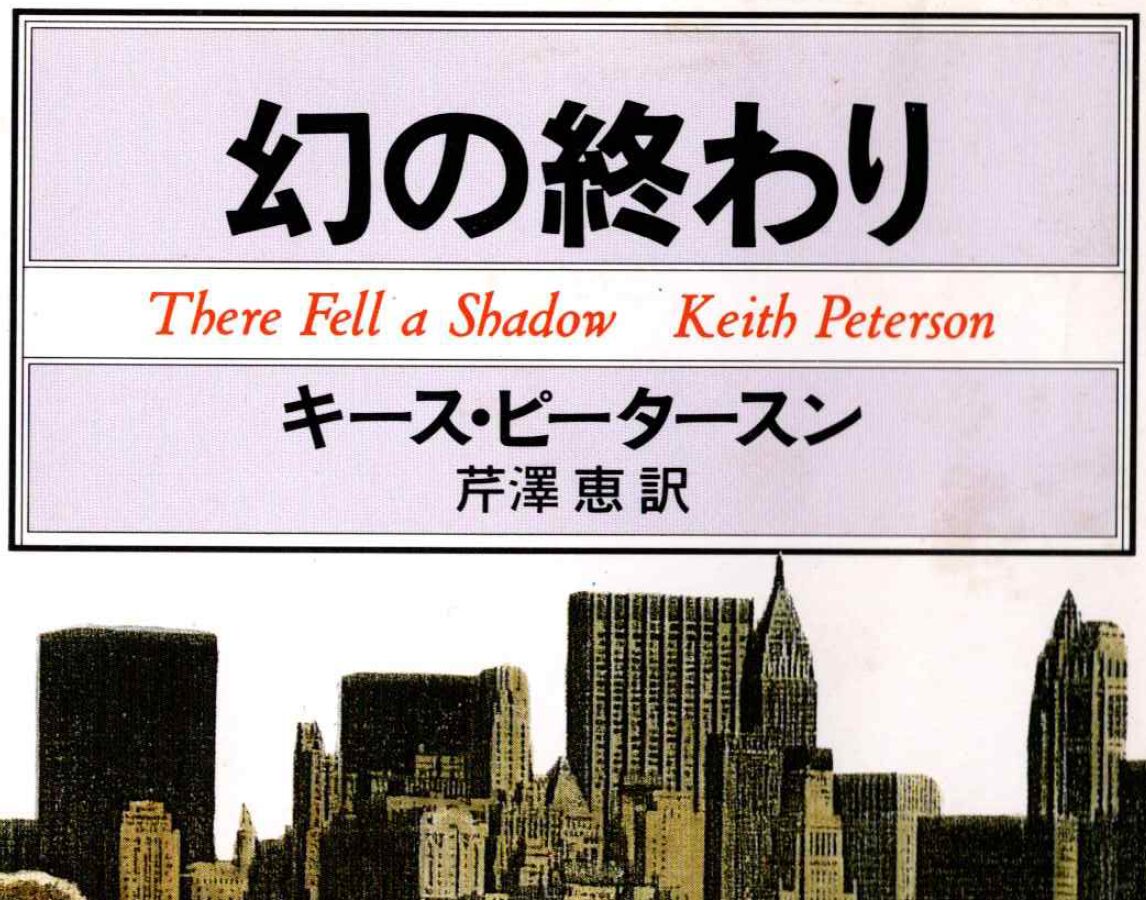ニューヨークの敏腕記者が主人公のハードボイルド・ミステリー、キース・ピータースンの〈ジョン・ウェルズ記者〉シリーズーー。きょうは2作目「幻の終わり」(原題:There Fell a Shadow)を紹介します。前作と趣が大きく異なり、暗殺者に追われるなどスリリングな展開で、主人公を慕う女性記者の絡みもいよいよ始まります(2024.1.13)
〈PR〉
内戦取材とスクープ
前作「暗闇の終わり」(創元推理文庫)が田舎で起きた高校生の連続自殺の謎を解き明かすのに対して、こちらは、かつてアフリカの小国で起きた内戦を取材したジャーナリストたちの「愛と裏切りの記憶」(創元推理文庫の背表紙から)がテーマです。
ウェルズが記事を書き終えて同僚のランシング、マッケイとともにプレスクラブで酒を飲み、別のグループに知り合いがいたため合流する場面から始まります。
別のグループの3人ーーホロウェー、ウェスラー、コルトは10年前にアフリカの小国セントゥーの内戦取材で名を挙げた戦争ジャーナリストたちだった。
「万一、反政府軍が政権を掌握するようなことにでもなれば……。これは特ダネ中の特ダネだ。そしてそれは現実のことになった。おまけにおれたちはその場に居合わせたというわけだ」
ホロウェーは反政府軍の指導者たちのインタビューに成功し、セントゥー関係の記事ではじめて一面を飾った。「アメリカが取るべき態度について議会が紛糾しているとき、議員たちが資料として振りかざしていたのはそのホロウェーの記事の切り抜きだった」
一方、ウェスラーはセントゥーの記事でピューリッツァ賞を受賞した。
「ほとんどの記者が命惜しさに続々と脱出していくなかでマングレラから記事を送り続けたんだ。マングレラは当時セントゥーの首都だった。その首都が陥落すると、反政府軍が……なだれ込んできて、マングレラは密告と銃撃戦の修羅場となった。アメリカのヘリコプターが去ってしまうと、あとは……そのあとを見届けた者は誰もいない」
「そう、ウェックス以外は」
だが、ホロウェーもウェスラーも戦争取材から引退。いまも戦地を駆け回っているのはコルトひとりだった。
「おれのエレノア」
コルトと気が合ったウェルズは、酒席がおひらきになった後もコルトのホテルに付き合った。ふたりとも明け方近くまで飲み続けたが、ウェルズは酩酊状態のコルトがこうつぶやくのを聞き逃さなかった。
「エレノア、エレノア、おれのエレノア」
その翌朝、コルトは殺された。コーヒーを持って来たベル・ボーイにナイフで刺され、ベル・ボーイは居合わせたウェルズにも襲いかかってきたが、ウェルズは激しい格闘の末、からくも殺されずに済んだ。
なぜコルトは殺されたのか。
ウェルズは、コルトがつぶやいた「エレノア」の名を頼りにセントゥーでの出来事を調べ始めた。
そして、「エレノア」がセントゥーで政府軍、反政府軍、市民の分け隔てなく国外に脱出させる地下組織を運営していたイギリス人宣教師のことで、コルトと恋仲だったことや、首都陥落の混乱の中でコルトがエレノアを救出しようと必死で行動したにもかかわらず、果たせなかったことを探り当てる……。
しかし、「愛」の記憶がコルト殺害とどう関係するのかわからない。ウェルズはその後も執拗にコルトの殺害犯に狙われる。
「愛」が理由ではないとしたら……。ウェルズが探り当てた「裏切り」の真実とは!?
本筋の紹介はもうこれで十分でしょう。とにかく途中からは一気読みです。
ゴッドリーブとワッツ
本書では、その後のシリーズを通じて重要な役割を果たす登場人物が出てきます。
ひとりはゴッドリーブ警部。ウェルズに「ランシングはいい娘さんだ」「嫁さんにもらえ」と冷やかしながら、ウェルズに好意を抱いている刑事です。
もうひとりは、ウェルズが悪徳ぶりを記事にしたせいで警部から降格させられたワッツ警部補で、本書の中盤でウェルズと悶着を起こします(これがシリーズ最終作「裁きの街」の伏線となります)
コルトは殺される前夜にレスター・ポールという男に「お前は死んだはずだ」と絡み、警察が重要参考人として追っている中で、ウェルズはポールと接触します。そのことでワッツはウェルズを逮捕、取調室で会話の内容を吐かせようとし、ウェルズは守秘義務を盾に拒否します。
「これは記者証だ」
ワッツとウェルズが衝突するシーンを紹介しましょう。
眼をぎらつかせ、顔を真っ赤にしながら、彼はジャケットの内側に手を突っ込んだ。
一瞬、ピストルを引き抜いてわたしを撃ち殺すのではないかと思った。が、ワッツが取り出したのは警察バッジだった。彼はそれをかざしてわたしに見せ、甲高い声でわめいた。
「これがなんだかわかるか、このくず野郎?」彼の口から唾が飛んだ。「これがなんだかわかるか? これはバッジだ。本物のバッジだ。いいか、おまえは警官を殴ったんだ。たった今、その手で」
わたしは札入れを取り出し、ワッツにかざして見せた。「これは記者証だ、トミー。わたしの職業は憲法で保護されてる。あんたの職業は憲法に記されてもいない」
どうです? かっこいいでしょう?
このあと、ワッツがウェルズに暴行を振るって床に叩きのめした直後、ゴッドリーブ警部が登場します。
「どういうことかね?」
ワッツはわたしを指し示し、藪から棒に言った。「ウェルズは今夜、レスター・ポールと秘密会議を開いた」
「ほう? おたくはいつからコルトの件の担当になったんだね?」
わたしを指していたワッツの腕から力が抜け、だらりと垂れさがった。「あんたは今日はもう帰ったと思ったんだ」
「女房に言って、我が家にも電話をつけさせるよ。今度から電話してもらえるようにな」
「まあ、聞いてくれ……」ワッツに言えたのはそこまでだった。彼はゴッドリーブの顔を見て口をつぐんだ。
ワッツとゴッドリーブの静かなる対決シーンです。これもシリーズ最終作「裁きの街」につながります(再読したら紹介しますので、しばしお待ちを)
彼女はいい匂いがした
さて、最後にランシングとウェルズのことに触れましょう。
前作(暗闇の終わり)では、会社の同僚の趣が強かったふたりですが、本作からランシングのウェルズへのひそかな想いが随所にあらわれてきます。
暗殺者と格闘して傷だらけになったウェルズに対し、記者仲間たちは駆け寄り、ねぎらい、最後にランシングがひとり残る。
彼女はいい匂いがした。その日のランシングは淡いピンクのスラックスにストライプの入ったプルオーヴァー・シャツという格好で、それがよく似合っていた。活気に溢れ、輝いて見えた。が、そうやって眺めているうちに、彼女の眼が潤んできた。ランシングは片手を口のところに持っていった。その手は震えていた。
「よせ」とわたしは言った。
「だって、死人みたいじゃない」と彼女は言った。
ランシングはその後も、ウェルズに栄養をつけさせようとベーグルを無理に食べさせたり、コルト事件の担当を引き受けてウェルズをコルトの殺害犯から遠ざけようとしたり、ランシングの一挙手一投足がウェルズへの恋心をうかがわせる描写がはさまれます。
レスター・ポールの居場所がわかって警察が急行するものの、取り逃がす場面を取材したふたりの場面も紹介しましょう。
早朝版の締め切りに間にあわせるには、急いで記事を仕上げなくてはいけなかった。ふたりの署名でわたしがリードを書き、ランシングはそれまでに調べたレスター・ポールに関する情報をまとめた。そのふたつは相乗効果を発揮したーー〈脱獄の天才、ニューヨーク市警のまえで手並みを披露〉。いい記事になった。
(略)
ふたりとも疲れていた。どちらも黙ったままグラスの中身を見つめていることが多かった。しばらくして、ランシングは笑みを浮かべると、長いブロンドの髪を肩から背中のほうに払いのけた。
「どうした?」とわたしは言った。
彼女は気にしないでと言うように手を振ったが、それから思い直したように言った。「考えてたの。あんなふうにふたりで仕事をしたのって、久しぶりだなって」
わたしだって若くない
もうすこし続けましょう。
「どうしてそんなにこだわるの?」しばらくして彼女は言った。「コルトのことだけど」
(略)
「ああ。少なくとも、彼には生きていく目的のようなものがあったと思う。そのためなら必死になれるものが。なんだかひどく惜しい気がする」わたしはドアの取っ手に手を伸ばした。「あるいはわたしが年齢を取りつつあるというだけのことかもしれない」
「あなたはそんなに年齢じゃないわ」とランシングは言った。彼女はわたしのほうに顔を向けた。その顔に街灯の光が当たっていた。ブルーの眼からは鋼鉄のような光が消えていた。「それにわたしだってそんなに若くないわ」
(略)
ランシングは傷つきやすそうな眼でわたしのことを見つめ続けていた。彼女は美しかった。いい匂いもした。
ふたりは続く3作目「夏の稲妻」で、どこまで近づくでしょうか。乞うご期待です。
読め、読め、読め。
なお、これは前作「暗闇の終わり」の原稿に追記しようか迷ったのですが、本書の文庫解説を執筆した池上冬樹氏が「暗闇の終わり」で書いた自身の書評を再掲して、ローレンス・ブロックの〈探偵マット・スカダー〉シリーズに比肩する傑作と絶賛しています。
当時、多くの人がこのシリーズに熱くなったことがうかがえる文章ですので、ここに一部を引用します。
もう読んだだろうか? キース・ピータースンの『暗闇の終わり』である。これには酔ってしまった。文体にである。 語り口にである。主人公の新聞記者ジョン・ウェルズはほとんどマット・スカダーではないか。スカダーは誤って殺した少女の面影を消すことができず酒を飲むが、ウェルズは若くして自殺した娘を救えなかった自責の念で酒を飲む。屈折した中年男の内面が物語にさまざまな陰影をなげかけている。
(略)
いい作家の、いいシリーズがスタートした。読め、読め、読め。
(しみずのぼる)
〈ジョン・ウェルズ記者〉シリーズはこちら
・傑作”記者もの”の第1作:「暗闇の終わり」
・記者が探り当てる愛と裏切りの記憶:「幻の終わり」
・”そんな眼で…”ににじむせつなさに酔う:「夏の稲妻」
・「新聞社の取材です」に快哉:「裁きの街」
〈PR〉